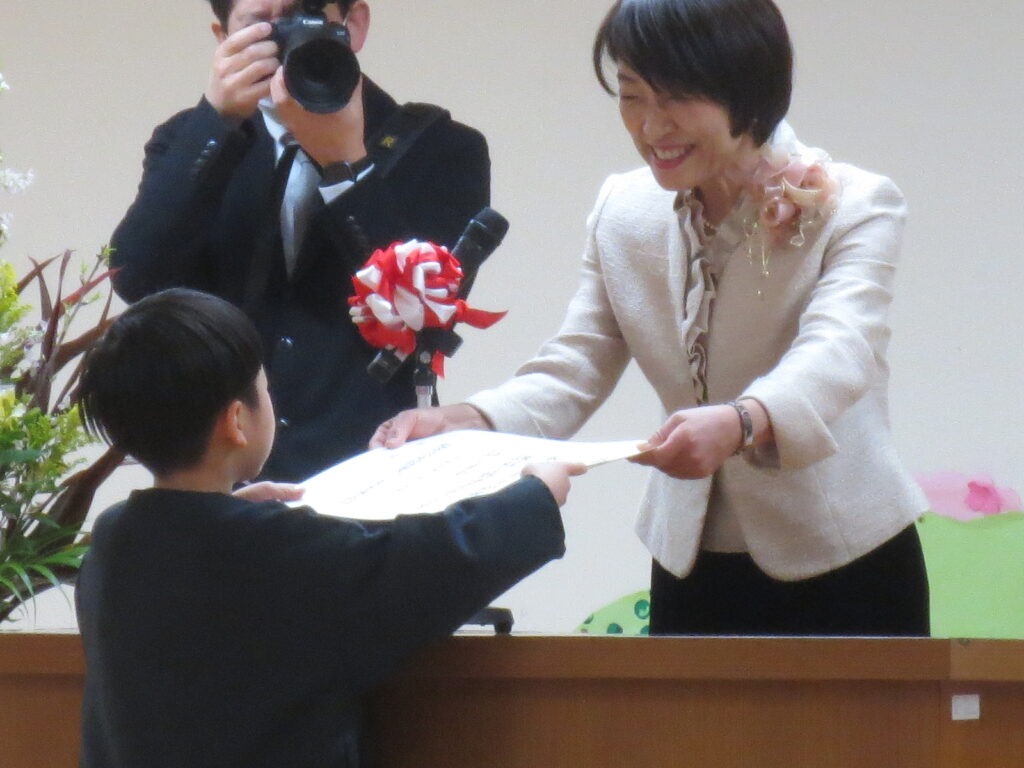2025.12.16
2025.12.16
もうすぐ,七夕・・・。「たなばた」は漢字で「七夕」と書くのはどうしてかな?と考えたこと,誰でも一度はありそうな漢字の謎です。諸説あるのですが,旧暦の7月7日の夕べに行うようになり「七月七日の夕べ」=「七夕」となった...といういわれもあります。
そして,「七夕」というと織姫と彦星のこんな絵柄を思い浮かべるのではないでしょうか。
子どもたちの七夕イメージは,初めから「七夕=(イコール)織姫・彦星の物語」というわけではなく,子どもたち自身が,いろいろ見聞きしたり,絵本を読んだりして,体験を積み重ねる中で,「織姫と彦星の七夕物語」を知っていくのです。年少組の,彦星,織姫のイメージはまだ少ないので,先生たちは紹介したようなイラストを今は飾っていません。
先生が,「ちいさなちいさなお星さま。どこにいるのかな?」と子どもたちに語りかけます。
手の中にだいじにだいじに何かをつつんだ先生が,小さな声で子どもたちに話しています。そっと手をひらくと,そこには小さなお星さまがありました。「かわいい」「お星さまほしい」子どもたちが口々に言います。
「ここにある」「ほら,きっと,ここだよ。せんせいはここでジャンプしていた。」
みんなで上を見ながら,「ここかな?あっちかな?」と話しながらお星さまをさがします。
先生が,「夜,おうちの人と一緒に空をみてごらん。星さまがきらっと光っているのが見えるかもしれないよ。」と話してくれました。子どもたちは,「お星さま見えるかな。」「見たいな。」「ちいさいのかな。」と,お星さまの世界にどきどき。美しいものを想像して,心が揺れ動く瞬間です。
年中組は,飾りをとんどんつなげて長くしています。「どの色にしようかな。」
「こんなにつながった。」「次はどうしようかな。」「もっときれいにしたいな・・」想像はどんどん膨らみます。
 _
_
年長組は,もっと難しい形に挑戦しています。くるくる丸めて,立体的にしています。
 _
_
紙を折って,素敵な色を付けました。「こう折るとすてきな模様になる」と気が付きました。さあ,これからどんな飾りができるのかしら。
学年が上がるにつれて,複雑な折り方ができるようになり,いろいろな模様が作れるようになっています。
【6月30日のきゅうしょく】ごはん,こんさいじる,ますのしおやき,アーモンドあえ,ぎゅうにゅう,すいか
おほしさまをさがして,年少組もたなばたのもようつくり。初めて「のり」を使いました。ちょっとずつ指につけて・・・。



 _
_