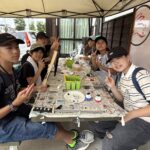2026.01.09
2026.01.09
5年生が,理科「天気の変化」の学習の一環で,雲作りに挑戦しました。この実験は教科書には載っていないのですが,海老名教諭が実験方法を調べ,子どもたちにぜひ見せてあげたいと思ったとのことです。鉄製スタンドに固定したペットボトルの口に,空気入れのピンを刺したゴム栓をします。ペットボトルは高圧に耐えられる炭酸飲料用で,中には少量の水を入れます。いったい何が起こるのか?全員が注目する中,代表の子が空気入れを何度も押すと・・・「バンッ!!」「わあー!」ゴム栓が吹き飛んで,ペットボトルの中が雲のように真っ白になりました(1枚目の写真)。海老名教諭は,「雲はどうやってできるの」「雲は何からできるの」と子どもたちに考えさせました。自分の考えを発表させた後の話し合いを通して,「海水が蒸発して水蒸気になり,上空で冷えて雲になる」という推論をまとめることができました。
この実験の原理は小学生レベルではありません。空気入れでペットボトルに空気を入れることで「空気の断熱圧縮」を起こしてペットボトル内の温度を上げ,水の一部を気化させます。ゴム栓が吹き飛んだ瞬間,「空気の断熱膨脹」が起きてペットボトル内の温度が急激に下がり,水蒸気が細かい水の粒となって雲のように白くなるのです。教科書には載っていませんが,今日の子どもたちの驚いたり喜んだりした反応を見ると,ぜひとも毎年やらせたい実験だと思いました。