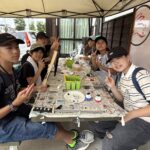2026.01.09
2026.01.09
昨日3時間目に,4年理科「ものの体積と温度」の公開授業を行いました。白南中学校の先生が参観に来られました。初めに,本田教諭がマヨネーズの空容器の口に石けん水を付けて押したところ石けん水の膜がドームのように膨らみました。子どもたちは当たり前と言った表情で「空気を押したから膨らんだ。」と答えました。次に,「試験管でやったらどうなる?」と聞いたところ,やはり当たり前のように「そのまま。」「ガラスは押せないから。」と答えました。「じゃあ,やってみよう。試験管を両手で握ってごらん。」・・・「うわっ,膨らんだ!」「なんで?」「あっためたから?」 学習課題は「石けん水をつけた試験管を温めるとシャボン玉がふくらむのはなぜだろうか。」と設定しました。子どもたちは,「空気が上に上がっていくから。」「蒸発したから。」「空気がいっぱいになったから。」と予想し,検証実験を3種類行って追究しました。参観していて,子どもたちの科学的思考力や論理的思考力が高まっていくのが感じられる授業でした。
長くなるので詳しく紹介できませんが,最後の検証実験は,試験管の底を切断して上下が開口した状態で実験をしました。本田教諭は,この実験をぜひ行いたいと言ったのですが,試験管はとても丈夫に作られているので簡単には切断できないのです。相談を受けた私は,パイプカッターやガラス切りを使って試してみましたが傷一つ付けることができませんでした。インターネットで調べたところ,ルーターにダイヤモンドカッター(実際はダイヤモンドではありません)を装着して試験管をゆっくり回転させながら傷つけていくと切断できることが分かったので,早速やってみたところ見事に切断できました(画像3枚目)。削れたガラスの粉じんを吸い込んでしまい気分が悪くなりました。ゴーグルとマスクの着用が必要です。画像4枚目は,本田教諭,田村教諭,高橋教諭が放課後に試験管切断を行っているところです。このように,子どもたちから見えないところで,教師は指導方法を研究したり準備をしたりしているのです。