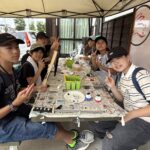2026.01.09
2026.01.09
4年生の教室後ろの壁面に国語の学習を記録した「ごんぎつね新聞」が掲示されています。私も27年前に「ごんぎつね」を指導した思い出があります。保護者や地域の皆様も,小学生のときに「ごんぎつね」を学習したのを覚えていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。いったいいつから「ごんぎつね」が国語の教科書に載ったのか調べたところ,なんと昭和31年(1956年)に大日本図書の教科書に載ったのが始まりだと分かりました。昭和55年以降は全ての教科書会社の教科書に載っているとのことです。現在73歳以下の方は「ごんぎつね」を学習した方がいらっしゃることになり,現在49歳以下の全ての方は学習したはずです。
「ごんぎつね新聞」には,学習の内容や子どもたちの考えが載っていて,どのような授業が為されたのかが一目で分かります。毎回,「BESTごん日記」という欄に,子どもが書いた学習の振り返りが紹介されています。本田教諭に,「普通の授業ではここまでやらないのに,なぜ時間や手間がかかる新聞を作ったのですか。」と聞いたところ,「国語の単元の中で,1つは特に力を入れて指導したいと考え,ごんぎつねを選んだのです。」とのことでした。新聞の最後には,約2週間で子どもたちの考えがどのように変容したかが「考えの成長」としてまとめられています。これを読んで,子どもたちが確実に物語文の読解力を身に付けたことが伝わってきました。
(振り返りノートから)「ごん日記で,ごんになりきってみたり,兵十やごんの気持ちを自分ごとみたいに考えられるようになった。」「(前略)どんどん勉強していったら考えが変わりました。ごんはいたずら好きだけど,すてきでかわいそうなきつねに変わりました。勉強していくうちに,こんなに変わるんだと自分自身でもびっくりしています。」「『青いけむりが,まだつつ口から細く出ていました。』の文章は,ごんの命が消えかけているのを表しているのが分かりました。」