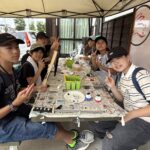2026.01.09
2026.01.09
6年生が理科で「月の形と太陽」を学習しています。インターネットで検索すれば,鮮明な月の写真を見ることができますが,私は天体望遠鏡を使って自分の目で見せることが大切だと考えています。パソコンの画面で見る平面の月に比べ,天体望遠鏡で見る月のクレーターは大気の微妙な揺らぎの中で立体的に見えます。月は毎年,月日によって見える位置が変わります。本当は日没後の夜に観察すると,まるで月に手が届いて触れるような感動を味わえるのですが,学校では登校直後か下校直前に見せるしかありません。いずれも太陽が出ていて青空の中で観察するので淡い月の観察になります。今朝は月齢19日で観察に絶好とは言えない条件でしたが,晴れていたのでベランダで月の観察に挑戦しました。人間の目が暗闇の中で徐々に慣れて見えるようになるのと同様に,昼間の月を天体望遠鏡で見るときも,しばらく見ていると瞳がわずかに開いてクレーターが見えるようになります。私は慣れているので,すぐに無数のクレーター,直径約85kmのティコ(クレーター),ティコから放射状に広がる最長約1500kmの光条(レイ)などが見えたのですが,子どもたちは初めての体験でなかなか分からなかったようです。結局,クレーターが見えた子は一人,なんとなく見えたという子が一人だけでした。残念! 次のチャンスは21日(月)の朝です。月齢22日で下弦の月(半月で太陽光が真横から当たるのでクレーターに影ができる)となるので,最もクレーターが見えやすい条件となります。子どもたち全員が見えるように,晴れることを祈っています。 参考までに,数年前に撮影した月の写真を掲載します。下段左が夜撮影,右が昼撮影したものです。こんな感じで観察することができます。